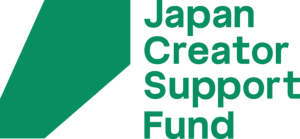【批評プロジェクト 2025】最終選出作品発表!
2026.1.15 (Thu)
KYOTO EXPERIMENT 2025では、村川拓也「舞台版『テニス』」を対象としたレビューを募集する批評プロジェクト 2025を実施しました。最終選考の結果、三田村啓示氏による応募作「告白と謎」を選出いたしました。
審査およびメンターを担当した梅山いつき氏からの全体講評を掲載いたします。
なお、最終選出作および一次選考通過作は演劇批評誌「紙背」WEBでも掲載されます。
【最終選出作】
三田村啓示
「告白と謎」
【一次選考通過作】
張藝逸
「声と身体のあいだで—村川拓也の舞台版『テニス』が示す当事者との距離—」
宮口祥子
「虚構とリアルの先に見たもの」
【全体講評】
本年は村川拓也さんの演出による舞台版『テニス』が課題作品となり、投稿件数は昨年度よりも増えました。この批評プロジェクトの認知度が高まり、KYOTO EXPERIMENTおよび課題作品に関心を寄せる方が増えてきている結果だと嬉しく思っています。
『テニス』はそのやわらかな雰囲気と裏腹に、どういう作品なのか、そのディテールや構造をパーツに分解しながら、言葉を当てはめ、第三者に伝えようと思うと、なかなかな曲者作品で、なぜあのような上演スタイルをとっているのかというところについて、作品の内容とともに説明するのはいくつかの手続きを要します。
もう一つ、本作は演劇作品における主体の問題をテーマにしてもいます。3名の若者が自身のルーツや一生付き合わなければならない病について告白しますが、それらは録音された音声になって観客に届けられ、観客の前に現れた身体とは距離が置かれています。繊細な内容を聞いた観客はつい、3名について「わかった」ような親近感を抱きますが、同時に、それが録音であり、かつ、その内容と一致していることを疑いようもない身体が舞台という虚構の空間に置かれていることを意識させられもするため、「ちょっとまてよ」と、「わかった」ような気持ちにブレーキをかけることになるのです。
今回、投稿された方たちは全員、この「ちょっとまてよ」をいかに整理し、言語化するかに苦労されていました。興味深かったのは、書き手もまた、本作について論じながら、自身の観客としての立ち位置や主体性を問うていたことです。それこそもしかしたら、村川さんが目指していたことなのかもしれません。
今回、掲載となった3名の方は投稿時の文章から大きく変化し、考察をより深め、丁寧に作品を論じています。3本とも優れた批評ではありますが、ハンナ・アーレントの理論と結びつけることで、作品世界をより拡張してみせた三田村さんの批評を最終選出作品に選ばせていただきました。
来年度もこのプロジェクトが継続されるようでしたら、ぜひ多くの方に参加いただき、作品をめぐって一緒に考える時間が生まれると嬉しいです。投稿いただいた方には全員にコメントをお送りしています。今回、投稿してくださったみなさん、ありがとうございました。
【講評】
三田村啓示さん「告白と謎」
三田村さんの批評は冒頭、左京東部いきいき市民活動センターという本作の会場に着目するところから出発している。それは「りっぱ」ではないところだとあえて指摘し、最後、しっかり伏線回収的に、この会場でなければならなかった理由を述べている。改稿にあたっては文章構成に苦労したようだが、その分、緊密な構成に仕上がった。三田村さんも他の書き手と同様に、本作の語りを分析している。それが録音された音声であることについての考察がユニークで、今ここで発せられているわけではない「オフの音」だからこそ、隠された「内面」である印象を強め、親密な告白であるかのように観客に思わせる効果があるのではないかとする。批評後半ではこの演出効果をハンナ・アーレントの「現われの空間」に結びつけて深く考察していく。その際、2つ目のシーンに出てくる登場人物がテニスボールを観客と受け渡したり、握手をしたり、会場の窓を開けるといった行為を取り上げ、それらの予期せぬ観客への働きかけが、「現われの空間」の出現に寄与していると分析する。2つ目のシーンの登場人物の行為は特に劇的でもなんでもないが、それゆえに、何を目的にしているのか疑問に思った観客は多かっただろう。三田村さんの分析はその一つの回答として非常に説得力が高かった。また、冒頭言及した会場のことと「現われの空間」をめぐる議論を結びつけ、公共的空間という点で、会場となった左京東部いきいき市民活動センターという場所は、様々な活動においてローカルの公共性を担っている、「りっぱ」な場所だったと結論づける。ここで、冒頭触れた会場の話が伏線回収される。もう1点、重要な指摘として、この舞台には生い立ちを語る3名以外に、ただテニスの練習をするだけの2人の若者がいることの意味が論じられている。三田村さんは、2人の存在があるからこそ、3人の出演者の内面と半生の「告白」に立ち会うということが、どこか運命的な出会いの感触に似ていると結ぶ。作品の細部まで論じ切った力作である。
張藝逸さん
「声と身体のあいだで—村川拓也の舞台版『テニス』が示す当事者との距離—」
張さんは自身が在日外国人の女性としてこれまで多くのドキュメンタリー演劇におぼえてきた違和感と、それに比して本作はそういった居心地の悪さを感じなかったのはなぜなのかを考察している。特に、本作における声と身体の分離に着目し、この構造が「当事者を類型化しない」ことに成功していたために、他のドキュメンタリー演劇のような違和感や居心地の悪さを感じなかったのではないかと結論づける。本作を見た多くが、テニス(練習だけでなく、ボールを拾い、投げる、または、マネージャーとして練習に立ち会うことも含む)という目の前でなされる行為と、音声によってもたらされる、主要な3名の登場人物たちの生い立ち、そして最後の締めとして告げられる3名の名前という、語りの内容と身体行為の不一致に気づくが、それが一体なんのための仕掛けなのかまで考えを整理する余裕はないまま、上演は終わってしまう。張さんは、この仕掛けによって、マイノリティの「苦労」が整理され、マジョリティにとって消費しやすい形に上演が加工されてしまうことを回避していると述べる。この考察も鮮やかではあるが、後半、「マブイ込め」という本作で触れられている風習に言及し、それと多文化社会における「理解」の問題との重なりを指摘している点に独自性がある。そこに村川が観客に求める「呼びかけの継続」と「その不確実性の自覚」が込められているとする主張は新鮮だった。一方、呼びかけに応じるかどうかは出演者の側に委ねられているという指摘にやや説得力が欠けるところもあった。主張したいことが先行してしまい、それを立証するための十分な材料がそろっておらず、最後、拙速な論述になってしまったが、もう少し言葉を尽くすことで十分説得力のあるものになっただろう。
宮口祥子さん「虚構とリアルの先に見たもの」
宮口さんは上演中、自分や他の観客たちが拍手をしかけた手を途中で引っ込めてしまったのはなぜだったのか疑問に思ったところから、本作の考察をはじめている。本作で語られる登場人物たちの生い立ちはリアルな告白なのか、嘘としての演劇なのか?虚構と現実の境界線があいまいなために、拍手をするのをためらってしまったのではないか。では、その語りはどのようなものだったのか。宮口さんはそれが直接、3名の登場人物の口から語られるのではなく、録音された音声として間接的に流れてきたことにも注目し、ラジオや音楽のように流れてきたからこそ、聞きやすかったのではないかと述べる。しかし、聞きやすかったことからといって、登場人物との距離感が縮まったのではない。むしろ、距離は広がっているのではないか。たとえば、スマホの画面ばかりを見つめ、目の前の世界から切り離されているように、わたしたちは現実と虚構の世界を日常でも行き来しているが、それによって、自他の間には「近くて遠い距離」が生まれているのではないか。宮口さんはそう考察し、本作の語りによって、自らが身につけてしまった習性と他者との分断が自らを蝕みはじめていることが露見し、空恐ろしく感じられたと結ぶ。拍手をためらったというちょっとした出来事から作品全体を振り返り、自他の距離感にまで話を展開していったところに豊かな想像力を感じた。距離感の話から、本作が他者との分断を表しているというくだりがやや駆け足になってしまった。また、作品描写の際に、宮口さんが受けた印象が中心になっているが、作中何が起こったのかと、それに対して何を感じたのかをもう少し切り分けて記述することも必要だろう。
(審査・メンター:梅山いつき)
メンタープロフィール
【批評プロジェクト 2025】
対象作品: 村川拓也
舞台版『テニス』
2025年10月9日 (木)-10月13日 (月)
https://kyoto-ex.jp/program/takuya-murakawa/
助成:クリエイター支援基金
協力:紙背