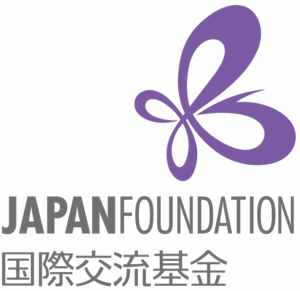マーク・テ / ファイブ・アーツ・センター
トゥアの片影
- 日時
10.4 (Sat) 18:30
10.5 (Sun) 13:00 ★♡
10.5 (Sun) 17:30 ☆◆
- 会場
- ロームシアター京都ノースホール
- 上演時間
75分90分
☞ 上演時間が変更になりました
- 料金
一般:¥3,500
ユース(25歳以下)・学生:¥3,000
高校生以下:¥1,000
ペア:¥6,500
- 言語
英語・マレー語(日本語・英語字幕あり)
マレーシアの伝説的英雄に見る
ロマンと神話とナショナリズム
現代マレーシアを代表する演出家でキュレーター、研究者のマーク・テが、自国の現代史の影を描いた演劇『Baling (バリン)』以来、9年ぶりに京都で公演。最新作はマレーシアで育った人なら誰もが知っている英雄「ハン・トゥア」の複層的な実体がテーマだ。
15世紀、マラッカ王国の黄金時代に活躍したとされる戦士トゥアは主君への忠誠心や勇敢さで知られ、時を経た今日ではマレー民族主義のシンボルへと変貌した。道路やスタジアム、コーヒーにトゥアの名が冠され、数多の映画や書籍で描かれてきたことでもおなじみだ。
マーク・テと彼が協働するパフォーマー、デザイナー、研究者のチームは、この英雄のイメージが歴史のなかでいかに変容し、時に国家の神話づくりに利用されてきたかを、各地に残るトゥアの痕跡をたどりながら探求。マルチメディアと楽曲を駆使し、時を超えた壮大なドキュメンタリー・パフォーマンスとして編み上げた。めぐった土地はバリ島からロンドン、沖縄まで。トゥアは本当に実在したのか、虚像なのか。ヒーローか、イデオロギーの体現者か。歴史的英雄になる方法とは?あなた自身の目で、その答えを探してほしい。
マーク・テ / ファイブ・アーツ・センター『トゥアの片影』
アーティストプロフィール

マーク・テ
クアラルンプール(マレーシア)
マレーシアのクアラルンプールを拠点とするパフォーマンス作家、研究者、キュレーター。ロンドン大学ゴールドスミス校芸術政治専攻で修士課程を修了。協働的で、多岐に渡るマーク・テのプロジェクトは、ドキュメンタリー的、思索的、生成的な形式をまとい、歴史のもつれや記憶、反地図学、政治的な内容を提示する。活動はおもにパフォーマンスの分野で行われるが、展覧会、教育、社会活動、執筆、キュレーションにも広がる。
マーク・テの作品と活動は、イルハムギャラリー(クアラルンプール)、OzAsiaフェスティバル(オーストラリア・アデレード)、シュピラート演劇祭(ドイツ・ミュンヘン)、ソウル・パフォーミングアーツ・フェスティバル、BIPAM(バンコク国際舞台芸術ミーティング)、YPAM(横浜国際舞台芸術ミーティング)、クンステン・フェスティバル・デザール(ブリュッセル)、MAIIAM現代美術館(タイ・チェンマイ)、コムニタス・サリハラ芸術センター(ジャカルタ)、東京芸術劇場、山口情報芸術センター(YCAM)、ファスト・フォワード・フェスティバル(アテネ)、MMCAソウル館、世界文化の家(ベルリン)、クアラルンプール舞台芸術センターなどで紹介されている。2024年には、プリンス・クロース基金/ブリティッシュ・カウンシル・フェロー賞「Moving Narratives」に選ばれた他、in-tangible instituteが実施するプラットフォーム「Pollination」の共同キュレーターを務める。

ファイブ・アーツ・センター
クアラルンプール(マレーシア)
マレーシアのアーティスト、活動家、プロデューサーによる、動的に活動するコレクティブ。現代芸術の状況における、オルタナティブな芸術様式や表現を生み出すことに尽力している。1984年に、ともに演出家のチン・サン・スーイとクリシェン・ジット、ダンサー/振付家のマリオン・ドゥ・クルーズ、劇作家のK・S・マニアム、そしてビジュアル・アーティストのレザ・ピヤダサによって結成。以来、マレーシア文化の複雑さと独自性を伝えようと、探求を重ね、ローカルな言葉と形式、伝統の融合を、グローバルな世界や近代、異文化交流との関係において実践してきた。それにより、芸術分野において、いくつもの影響と複数の歴史が混ざりあう中から生まれるマレーシアらしさの広がりに、貢献している。40年以上にわたり、ファイブ・アーツ・センターは、実験的で、異なる分野、異なる文化を横断する作品創作の最前線に立ち、次世代の芸術実践者のために機会を提供してきた。マレーシアでの生活に影響を与える現代の社会、政治、文化に関する問題が、上演、展示、クリエイティブなセミナー、リサーチのためのワークショップ、芸術に関する政策提言を通して凝縮されている。現在、コレクティブは、以下の異なる分野、世代の13人によって構成されている。
アン・ジェームス、ファイク・シャズワン・クヒリ、アイビー・N・ジョサイア、ジャネット・ピライ、ジューン・タン、Kubhaer T. Jethwani、リー・レンシン、マック・チャン、マリオン・ドゥ・クルーズ、マーク・テ、 Ravi Navaratnam、Suhaila Merican、シャムスル・アズハー
クレジット
パフォーマンス・ミュージシャン:Faiq Syazwan Kuhiri、OJ Law、Shariman Shuhaime
演出:マーク・テ
プロダクションデザイン:Wong Tay Sy
照明デザイン:Syamsul Azhar
マルチメディアデザイン:Syamsul Azhar、Bryan Chang
舞台監督:Armanzaki Amirolzakri
プロデューサー:June Tan
アシスタントプロデューサー・制作:Hoe Hui Ting
製作総指揮:ファイブ・アーツ・センター
助成:一般財団法人地域創造[舞台芸術を通して考える身体/歴史/アイデンティティ]
主催:KYOTO EXPERIMENT、国際交流基金
KYOTO EXPERIMENT × 国際交流基金「Sequence」事業
KYOTO EXPERIMENTスタッフ
テクニカルコーディネーター:小林勇陽
照明:宮島靖和(RYU)
音響:大久保歩(KWAT)
映像:福岡 想
衣装管理:新井海緒
日本語字幕翻訳:hanare × Social Kitchen Translation、Art Translators Collective (田村かのこ、春川ゆうき)
字幕オペレーター:河合有澤 京花
トーク通訳:齋藤 啓
制作:寺田貴美子(ロームシアター京都)