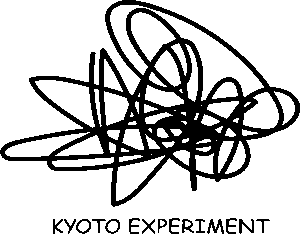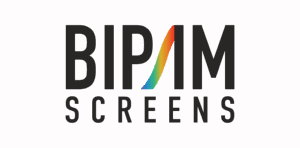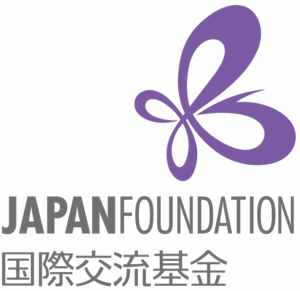Shifting Points
- 日時
[パブリック・トーク]
10.25(Sat) 11:00-12:00
[ワークショップ]
10.20(Mon) 18:00-20:45
- 会場1
- 京都芸術センターミーティングルーム2
- 会場2
- ロームシアター京都ノースホール
Bangkok International Performing Arts Meeting(BIPAM)、KYOTO EXPERIMENTおよび独立行政法人国際交流基金(JF)が共同で主催する、日本、タイ、東南アジアの次代を担うアーティストのインキュベーション・プログラム。公募にて選出された、多様なバックグラウンドで舞台芸術を創作する新進気鋭のアーティストが参加し、日本やタイをはじめとするさまざまな場所でのフィールドワークを通して互いの学びを共有しながら、自身の思考や実践方法を拡張していきます。
2025年度は、参加アーティストがKYOTO EXPERIMENT開催期間中に京都に滞在し、フィールドワークとパブリック・プログラムを行います。
[パブリック・トーク]
日時:10.25(Sat) 11:00-12:00
会場:京都芸術センター ミーティングルーム2
出演:参加アーティスト
聞き手:KYOTO EXPERIMENT 共同アーティスティック・ディレクター、ササピン・シリワーニット(BIPAMアーティスティック・ディレクター)、シリー・リュウパイブーン(BIPAMアソシエイト・アーティスティック・ディレクター)
料金:無料
[フィールドワーク&ワークショップ]
[フィールドワーク期間]
10.19(Sun)-10.26(Sun)
[ワークショップ]
Shifting Points 公開ワークショップ
☞ 日時
2025.10.20(Mon)
①18:00〜18:45 ホアン・アイン・グエン + 内田結花
②19:00〜19:45 玉井秀和 + ポンサトーン・プッタコート
③20:00〜20:45 アンナスタシャ・フェリナ + タナポン・アッカワタンユー
(各回45分。受付開始は各15分前より)
☞ 会場
ロームシアター京都 ノースホール
(住所:京都市左京区岡崎最勝寺町13)
☞ 参加無料
☞ 参加方法
各回定員が異なるため、ワークショップごとにご予約ください。複数のワークショップにご参加いただけます。
☞ 使用言語
英語・日本語 ※ワークショップは簡単な英語で進行しますが、場合によっては日英通訳のサポートも入ります。
ワークショップ詳細
18:00〜18:45「Day has come, but we are now underground.」
・ファシリテーター:ホアン・アイン・グエン(ベトナム)+ 内田結花(日本)
・定員:30名(先着順 / first come, first served)
・概要:歩く・立つ・座る・寝るなどのシンプルな動きから始まり、その動作の繰り返しや変化を通して、身体表現の可能性を探ります。ワークショップ中には時々照明を消し、暗闇の時間をつくります。暗闇と光の切り替えによって、身体や空間の感覚がどのように変わるかを体験します。そして最後には、参加者全員で約10分の即興パフォーマンスを行います。このワークショップでは、言語によるコミュニケーションを最小限に抑え、身体を通じた表現にフォーカスします。ダンスやパフォーマンスの経験は問いません。舞台芸術に関心のある方なら、どなたでもご参加いただけます。
※動きやすい服装でご参加ください。
※即興パフォーマンスで使用したい物があればお持ちください。なお、暗闇で光るものはご遠慮ください。
19:00〜19:45「Sound, Sense, and Story Beyond Language」
・ファシリテーター:玉井秀和(日本)+ ポンサトーン・プッタコート(タイ)
・定員:10名(先着順 / first come, first served)
・概要:言葉の意味にとらわれず、音・リズム・トーンに注目しながら物語や民話を語る、実験的なワークショップです。子供の頃、おじいちゃんやおばあちゃんから昔話を聞いた時、それはまず音楽として私たちの身体の中に入ってきたのではないでしょうか?言葉が意味である前に音である事を通じて、日本語・タイ語・英語など異なる言語のあいだにある音の響きを探り、それを表現に結びつけます。パフォーマンスの経験は問わず、どなたでもご参加いただけます。
20:00〜20:45 「t ta tab tabl table」
・ファシリテーター:アンナスタシャ・フェリナ(インドネシア)+ タナポン・アッカワタンユー(タイ)
・定員:10名(先着順 / first come, first served)
・概要:このワークショップでは、日常で慣れ親しんだ「物/オブジェクト」に光を当て、見つめ直す試みを行います。 物を単なる機能的な存在として捉えるのではなく、形や質感、そしてそこに結びついた個人的な記憶・歴史・感情を探ります。ワークショップでは対象物をじっくり観察することから始めて、そこから広がるイメージをもとに、テキストや身体表現へと展開させます。この観察・記述・想像のプロセスを通じて、対象物の新しい一面を発見してみましょう。パフォーマンスの経験は問わず、どなたでもご参加いただけます。
※観察の対象となる物は会場にて準備しますが、ご自身の持ち物をお持ちいただいても構いません。
参加アーティスト(ファーストネーム・アルファベット順)
アンナスタシャ・フェリナ
インドネシア
インドネシア・スラカルタを拠点とする振付家・ダンサー。
Studio Plesunganでパートタイム勤務をしながら集中クラスに参加し、アーティスティックな方法論を発展させている。彼女の作品は、社会的なトピックを探究しながら身近な現実を問い直し、再解釈することで、自身とその創作プロセスの一部を考察する。これまでに『Nyorog』(International Mask Festival 2021)、『Waktu Ku Kecil, Tidak Besar』(サリハラ国際舞台芸術祭 2024)、『Sebut Saja N』(Indonesia Bertutur Festival 2024)など、さまざまなフェスティバルで作品を発表している。
玉井秀和
日本
日本・京都拠点。劇団FAX 劇作家・演出家。
日本の昔話の構造をベースに、言葉と言葉を「ご縁」でつないで物語を構成し、日本の精神性を表現できる作品の創出を目指す。
京都大学において「祭りと住民の関係」を再考する研究をしており、宮崎、長野、ボツワナでのフィールドワークで得た知見は、演劇作品に反映されている。
ホアン・アイン・グエン
ベトナム
ベトナム・ニントゥアン拠点。ストリートダンサーとしてのバックグラウンドを持ち、身体を主要なメディアと捉えるなかで、日常の観察から生まれる対話に注目している。これらは、日々の身振りや会話を理想化することや、アイデンティティへの問い、出会った現象や超現実的な出来事の再構築まで、多岐にわたる探求につながっている。直感的なアプローチと慎重なアプローチの間を行き来しながら、パフォーマンス、映像、コンセプチュアルアートなどの手法を用い、自身の思索を身体を通して投影する。これまでに、Nguyen Art Foundation、IN:ACT2022、Nổ Cái Bùm Art Festival、KULTX Collaborative Spaceなど、多様なスペースでライブパフォーマンスや作品の展示・上映を行っている。
ポンサトーン・プッタコート
タイ
タイ・コーンケーン拠点。コーンケーン大学で舞台芸術を学び、アンサンブル俳優の衣装早替えに魅了されたことをきっかけに演劇の道へ。演劇の学びを通じて、物語を伝え、人間性を探究する深い力を発見する。
これまでの作品では、反戦、女性のエンパワーメント、平和といったテーマを扱い、演劇を意義ある変革のためのツールとして捉えてきた。
卒業後は視点を内面へと向け、心の平穏を探るとともに、故郷イサーンの文化的豊かさを再発見。現在は、イサーンの伝統文化——ラム歌、ケーン音楽、民話、詩など——に着想を得た作品を制作し、それらを新たな革新的な形で再構築することを試みている。
タナポン・アッカワタンユー
タイ
タイ・バンコク拠点。演出家・劇作家。タマサート大学で映画を専攻し卒業。
在学中に演劇クラブで活動し、演劇作品の創作を開始。2015年、パフォーマンスフェスティバルへの参加を目的に「Splashing Theatre」を設立し、以降現在まで作品を発表し続けている。これまでの作品の多くは、映画を中心とした多様なメディアを演劇作品へと翻案することを試みている。2016年、『The Disappearance of the Boy on a Sunday Afternoon』でIATCの最優秀作品賞および最優秀脚本賞を受賞。2022年には、Theaterfestival BaselのWatch&Talkプログラムに参加。
内田結花
日本
1987年大阪生まれ在住。振付家・ダンサー。
「上演環境や状況に振り付けられる身体」をテーマに、屋内外のあらゆる場で自作品を発表。主な作品に、日記を基にした振付を異なる環境や状況下で展開させていく『暮らしのシリーズ』(2019-23)、フィールドワーク素人たちによる鳩のコミュニティや生活をリサーチする『ニュー・フィールドワーク』(2023-)等。障害のある人もない人もともに活動するダンスカンパニーMi-Mi-Biに立ち上げより関わり、豊岡演劇祭公式プログラムとして上演した『島ゞノ舞ゝゝ』(2024)では、森田かずよと共同して演出を担う。
文化庁・NPO法人DANCEBOX主催「国内ダンス留学@神戸」2期修了。また、ダンサーとして、多様な振付家・作家の作品に出演している。
主催:KYOTO EXPERIMENT、BIPAM、国際交流基金
KYOTO EXPERIMENT × 国際交流基金「Sequence」事業