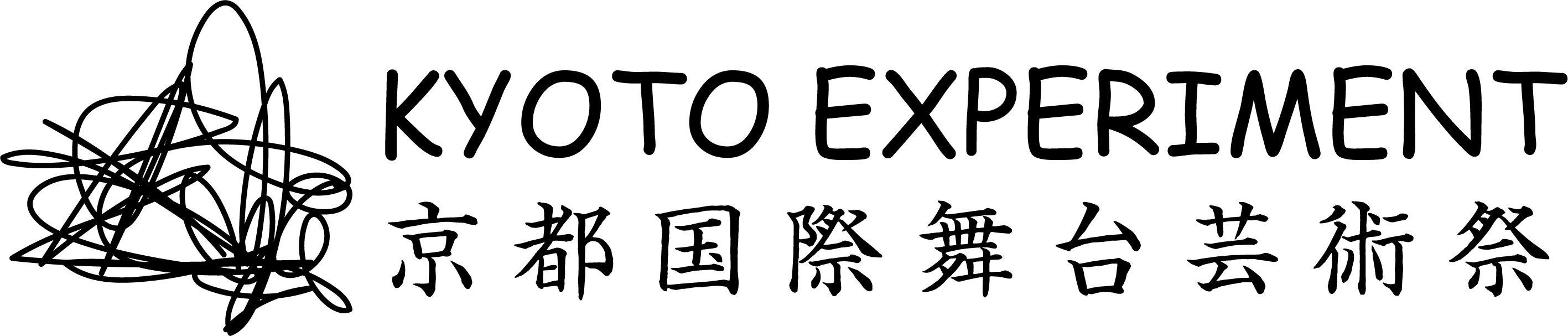magazine
KYOTO EXPERIMENTの成り立ち
2018.4.23
前KYOTO EXPERIMENTプログラムディレクター 橋本裕介
*本テキストは、『KYOTO EXPERIMENT 2011事業報告書』(2012年3月発行)所収の「仕組みであると同時に運動でもあるフェスティバルの姿とは」より抜粋、加筆修正
エクスペリメントの背景
KYOTO EXPERIMENTが始まったのは2010年秋だが、その成り立ちについて少し非公式な側面も含めて振り返ってみたい。
まずEXPERIMENT(=実験)という言葉を冠したフェスティバルとなったのは何故か、そのきっかけになる出来事がある。それは2005年の晩秋だった。
当時私は京都芸術センター演劇事業「演劇計画」を企画していた。この事業は2004年に始まったもので、2年目を無事に終え、次の展開を模索している時だった。その一環として行っていた演出家のコンクール「京都芸術センター舞台芸術賞」の審査委員を務めていただいていた、太田省吾氏の元へ今後の展開について相談したときのこと。彼は次のように提案してくれた。「いずれは演劇祭のような形にしてはどうだろうか。それも“実験的”な」。「実験的」…、にわかにはその言葉を飲み込めなかったが、そこに彼は言葉を続けた。「日本で“実験的”というと、今では特定のジャンル、それもかなり限られたものを指していて、時には侮蔑的なニュアンスも含まれる。しかし、芸術の分野で広く世界を見渡したとき、“エクスペリメンタル”と言えば、固定されたジャンルというよりはもう少し広く芸術的傾向・姿勢を指すものとして一定の理解がなされており、そのような名を冠したフェスティバルなどもある。」正確かどうか分からないが、凡そこのような趣旨だったと思う。
そのときの私がピンと来ていたかどうか怪しいが、「実験演劇」という言葉を当時は確かに“ややこしいもの”“めんどくさいもの”として捉えていたので、広く世界で捉えたときには必ずしも否定的なニュアンスだけではないという発言を受けて、印象に残っていた。ただ、フェスティバルを具体的に準備し始める2009年夏ごろまで、一旦このやり取りは記憶の隅に追いやられていた。
もうひとつの背景〜京都の舞台芸術状況
話を進める前に、この出来事の発端である「演劇計画」についても、更に時間を遡って振り返っておく。主催者である京都芸術センターは2000年の開設で、当時私は劇団の制作という立場でこの芸術センターの中にあるスタジオ「制作室」を訪れ、不思議な感覚にとらわれていた。
どういう感覚かといえば「なんて快適なのだろう」、そして「誰がこんなことを準備したのか?」というものだった。つい1年ほど前までは夜間に大学の教室に潜り込んで稽古をし、徐々に規制が厳しくなる中、いろんな大学を渡り歩くような状況だったからだ。それが芸術センターでは審査をクリアすると最大3ヶ月、場合によってはその期間1つの部屋を占有し、舞台美術を設置したままで稽古ができるのだ。
もちろん、設置者である京都市の意思で成り立ったことは事実だが、この運営のスタイルは芸術活動に携わっている人間が関わらずして実現しないはずだと思った。それが、「京都舞台芸術協会」という今ではNPO法人として組織されている京都の舞台人の集まりによる影響だということは、徐々に分かってきたことだった。この京都で最初の舞台関係者のネットワーク組織は、1996年鈴江俊郎や松田正隆、土田英生といった劇作家・演出家と制作者杉山準らが中心となって始められた。
私が京都に来て演劇の活動を始めた1997年ごろは、先述の鈴江と松田の岸田國士戯曲賞受賞や、芸術祭典・京で製作された『月の岬』の読売演劇大賞受賞などで京都の演劇界が盛り上がっており、加えてダムタイプが世界を舞台に活躍するなど、自分は観客としての立場だったが、何となくそのムーブメントは感じとっていた(もちろん、大阪でも民間の劇場が中心となってシーンを形成していた)。一方で彼らはそういった協会を組織して、舞台人としての意見を形成し外部に対してアクションを起こしたり、戯曲集『Leaf』などの雑誌を刊行したりしながら知的僚友関係を築いていた。
しかし当時の私には芸術上の“ムーブメント”と、この協会の社会的“アクション”が密接に関わっていることに気が付かなかった。というよりは、芸術上の“ムーブメント”が、社会的な“アクション”として変奏され得るということに想像が及ばなかった。そのため、先輩の舞台人たちの努力と行政の担当者の理解との極めて稀なバランスのもとに、芸術センターが成り立っていることを理解出来ていなかったのだ。それが、「快適さ」を異常なものと感じた原因である。
そこでハタと気付いたことが2つあった。ひとつは、その先達の築いた成果をただ甘受するのでは、そのうち食い潰してしまうことになるだろう、ということ。もうひとつは、芸術センターは場所であると同時に、事業体でもある。だから運用の方法についても、よりクリエイティブな方法を模索するべきではないか、ということだった。こうして芸術センターが創造の場としてより活性化するための提案を現場から行ってみたいと思い立ち、当時芸術センターの職員だった丸井重樹氏と共に「演劇計画」というプロジェクトをスタートさせた。
企画の構成は①作品のプロデュース、②若手演出家のコンクール、③演劇における批評的言語の3つを柱に行っていた事業だが、そのコンセプトを改めて説明すると、次のようになる。作品プロデュースを共にするアーティストとは2年間継続的に関わると決め、その時間の幅の中で思い切った取り組みに腰を据えて臨んでもらうこと。次世代を担う演出家を、言葉を尽くして選び、選考のプロセスを白日の下に晒すこと。作品の発表だけではなく、アーティストの関心や舞台芸術における諸問題を、多角的・批評的な視点で捉えるための議論の場を設けること。更にこういった言説に関わる部分は、報告書に収め記録として残すようにした。その都度自らにフィードバックを課しながら、3つの柱はブレないよう、一方で形を変えることは恐れずに行ってきた。これらの企画を膨らませる作業にあたっては、企画ブレーンを組織して、松田正隆氏や京都造形芸術大学の舞台芸術研究センターから森山直人氏や酒井徹氏、ほか多くの方々に参画していただいた(なお、舞台芸術研究センターも芸術センターとほぼ同時期にあたる2001年に開設されている)。
こうして事業を継続する中で、徐々に成果も目に見える形で現れてきた。このプロジェクトで製作した、前田司郎『生きてるものはいないのか』が岸田國士戯曲賞受賞、山下残『It is written there』がブリュッセルの世界的に著名なフェスティバルKunstenfestivaldesartsに招聘されるといったことである。その後の両氏の活躍は、舞台芸術に関心のある方ならご存知の通りである。また可視化しづらい部分でも、海外とのネットワークが着実に構築されてきていた。それらが現在このフェスティバルで、国内外の多くの優れたアーティストと共に仕事をすることが出来る種になっていることは言うまでもない。
地域で活動することへの意識〜次のステップへ
しかし運営している側そして観客の関心の高まりとは裏腹に、経済的にどのように継続するのかについては徐々に判断を迫られることになった。このプロジェクトはいわゆる興行だけでなく、収益性の見込めないシンポジウムなどの催しを企画の性質上重視していたため、その資金の多くを公的支援に頼っていた。ただ2008年ごろからは、公的支援の獲得に困難が生じ始めていた。既に2004年度から2007年度まで4年継続していたので、同様の企画に助成し続けることが難しいという理由がひとつ。審査では新規性が求められる、という指摘を受けた。更に、審査は基本的に東京在住の専門家が行っているため、より分かりやすくビジョンや成果が提示出来ないと目に留まりにくいのだ。ある助成金の審査に携わっている批評家から、次のようにはっきりと言われたことを覚えている。「橋本:今回とても面白く仕上がったので是非見に来て下さい。批評家:だったら東京でも公演やってよ。」非常に違和感を持ったことを書き留めておく。
また近年「地方の時代」と喧しく言われるようになって、芸術の分野でも地域のオリジナリティが評価の材料になり始めた。先述のような状況であるから、たとえ地域性と言っても、決して直接足を運ぶことのない東京の人々から見える「地方」の姿が求められているのだと肌身に染みて感じたことがある。「地方は田舎らしくあれ」ということなのだろうか、そうした雰囲気にも疑問を覚えた。このテキストを書くにあたり、1980〜90年代の状況も振り返っておこうといくつか資料をあたったが、むしろ公的支援のシステムが整っておらず、そのためかえって運営形態にもオリジナリティを発揮できた頃の方が、よほど一極集中が避けられていたのではないかとすら思う。これについては別の機会に触れたいと思う。しかし、いずれにせよ次の展開について考えるきっかけだったということは確かである。その地域のリソースをどのように活かし文脈として成立させるかは、周りから押し付けられるものではないはずだ。だからこそ、その文脈が存在しているのだと自覚するのであれば、それを質だけではなく量としても提示しなければ説得力を持たないと考えた。例えばある週末に観光を兼ねて2〜3本の舞台をまとめて観に来ることができる仕掛けにすれば、京都へ足を運ぶ動機としては成り立つのではないかと。それがフェスティバルという形態を選択したひとつの理由である。
フェスティバルを組織する
さて、2009年に入りこのフェスティバルの開催が正式に決定し、準備が始まった。このフェスティバルの運営主体は、京都市・公益財団法人京都市芸術文化協会・京都芸術センター・京都造形芸術大学舞台芸術研究センターで構成される実行委員会である。意思決定機関である委員会にそれぞれの組織から委員を出すだけでなく、職員もまたそれぞれの組織から派遣されて運営にあたってもらう仕組みである。これまで説明してきた通り、こと現代演劇・ダンスに関しては「演劇計画」を通じて、これらの組織はつながりを持って来たので、実行委員会を構成するのは自然の成り行きにも近かった。とはいえ、本来別個の組織である。仕事の流儀や価値観にそれぞれ異なるものを持っている。委員会の会議ではともかく、現場においてはその仕事のやり方の齟齬は当然顕在化し、さまざまな場で衝突が起こったことも事実だ。しかし私自身それは否定的に捉えていない。いずれかの組織の流儀に傾くのではなく、このフェスティバルにとって相応しい運営形態を模索することを通じて、翻って各々の活動を見直す契機になるからだ。ささいなことと思われるかもしれないが、広報媒体の製作と展開、チケット料金や販売方法、あるいは開場時間や入場整理の方法など、極めて具体的な運営の方法を議論し、共有することで、作品内容の側からではなく上演活動の側面から舞台芸術を捉え直す作業ができるのだ。もちろんまだ2回目を終えたに過ぎないので、「これぞ」と言える方法を見出したわけではない。今後も模索し続けなければならないが、少なくともこのプロセスは貴重な時間であることは間違いない。