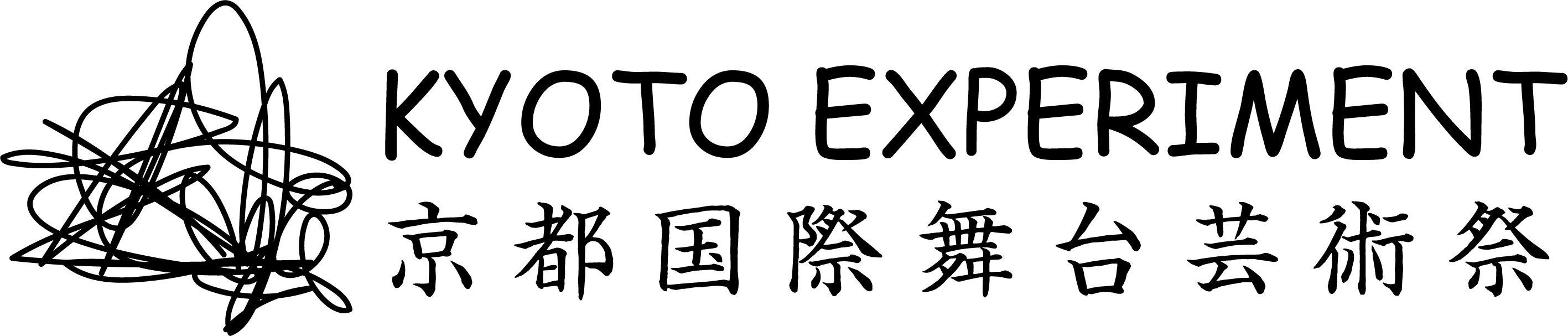magazine
ディレクターズ・メッセージ
2022.7.19
KYOTO EXPERIMENTが始まってから13年目、そして新型コロナウイルス感染症による世界的なパンデミックが始まってから3年目の2022年。この数年、舞台芸術や国際交流のみならず、社会生活において当たり前の前提であった直接的なコミュニケーションがままならない中、さまざまな分断がより明らかになったように思う。あいちトリエンナーレ2019を発端とした表現の自由についての議論、国際・国内社会における経済格差や人種間・宗教間における分断、ソーシャルメディアでたびたび話題となるある種の問題への糾弾、舞台表現の現場における不均衡な権威構造の見直し(の始まり)、そしてもっとも現在進行形であるのはロシアによるウクライナへの軍事侵攻だろう。これらの事柄が表現領域に多大な影響を与えるのは明白であり、さらに今後数年の在り方を大きく変えるだろう。私たちは世界中の友人たちと連携をとる中でその変化を観察し、フェスティバルの在り方にも反映させられたらと日々考えている。
今年度のこのフェスティバルの開催にあたり、いま、こうした時代を少しでもポジティブに乗り越えようとするキーワードを提案できるとしたら何かと考え、「ニューてくてく」と設定することとした。
役立つ⇔役立たない
KYOTO EXPERIMENTは、現在進行形の実験的な舞台芸術を社会に提示するプラットフォームであり、そうした舞台芸術がどんなところへつながっていくかを、参加する誰もが考えることを目指す場所である。実験的な舞台芸術は、必ずしも万人が共感できる表現ではなく、そのため商業主義的な表現に与しないことも多い。資本主義社会においては、メインストリームではなくいわばサブストリーム、あるいはオルタナティブストリームともいえるものであり、直接的な効果を多大に生むものではないかもしれない。しかし、サブのもの、あるいはオルタナティブなものがなくして、今日の社会の本質は成り立たない。もっと言えばこの二項対立もある種の虚構である。生物が種々の多様性を保ちながら生態系を支えあっているように、人間社会が柔軟性を持ちながらその強度を保つには、誰もが楽しいと思える、快適で「わかる」表現以外にも、多種多様なこれまでに観たことがないような表現が生まれ、たくさんの人の目や感性に触れながら受容され、その次の思考へとつながっていくことが重要である。大量の「いいね!」がついて短期的に利益をあげる「わかる」ものを目指すことで損なわれてしまう人間のイメージ力には、多くの場合一見無駄に思えるような寄り道が必要である。むしろ好奇心をもって「わからない」を大量に抱えて、人類はてくてく歩んできたのではないか。もはやそれは贅沢なことなのだろうか?このフェスティバルでは、現在進行形で実験されている表現を、いまを生きるみなさんと一緒に体験し、それが何なのか考えることで、私たちのありようと、これからのあり方を考えていくことを目指している。
「ニューてくてく」
「ニューてくてく」は、そうしたこれからの歩き方、意識の持ちようや問いの立て方を考えて設定したキーワードである。また、オンラインミーティングや配信での舞台鑑賞が普通になり、身体についての意識が希薄になったとともに、実際にある場所へと身を運ぶことが億劫になったこの数年を経て、私たちの身体性を具現化し、空間と時間を新たに共有し直すことを提案できるキーワードだと考えている。
「てくてく」は、日本語で歩くことを表象する言葉であるが、足を使って歩くことそのものをあらわす「てくてく」はもちろん、そこから発展して、移動することをあらわす「てくてく」、さまざまな意識における「てくてく」、異なる時間を行き来する「てくてく」、感情の「てくてく」、あるいはある規範やシステムへの動きをあらわす「てくてく」、など、いろいろな「てくてく」を考えることができる。「ニュー」は大きな変動の後、「てくてく」を新たに捉え、考えることをイメージして付けた。このキーワードは、包括的な「テーマ」ではなく、ラインナップされるすべての作品が、その下にきちんと収まるようなものではない。フェスティバルのプログラムに対する答えではなく、作品に対する新たなアイデアや視点を生み出すきっかけとなるような、提案や問いかけのようなものである。
今から約500〜700万年前、人類の祖先は4本足から2本足で歩くようになった。その理由は諸説あるが、人類にとって大きな転機となったことは間違いない。人はこれまでとは違う方法で空間を移動するようになった。今日のように形式化された舞台芸術ができる以前、そのルーツは移動と口承にあったと言えるかもしれない。文字や印刷が普及していなかった時代には、世界のほぼ全域で口づてに伝承が行われていた証拠が見つかっている。この場合、人々は歴史、文学、法律、歌、儀式などを、村から村へと歩くことによって伝えていた。
もちろん、人間が歩いて空間を移動する、あるいはA地点からB地点へ移動する理由は時代とともに変化している。私たちが暮らす現代社会を考えてみても、人が歩いたり移動したりする理由はさまざまだ。旅や巡礼のために歩く、政治的な行為として行進や抗議行動をする、あるいは何の目的もなく自分の思考を整理するために歩く。歩くという行為は、身体が空間を移動するということだが、この単純な行為を通して、私たちは過去を振り返り、いまを見つめ直し、未来を見つめることができる。
今年は観客のみなさんと、アーティストが作品を発表する上演会場、そしてミーティングポイントなどフェスティバルのさまざまな場所へてくてくして集まり、「ニュー」なてくてくを体験・想像したい。
プログラムについて
上演プログラムであるShowsでは、11演目を紹介する。
2つの作品では、「歩くこと」が直接モチーフとして使われている。日本のノイズミュージックの草分けであるメルツバウとヨーロッパから参加するミュージシャン、バラージ・パンディとリシャール・ピナス、そして写真家の志賀理江子によるビジュアルコンサートでは、志賀の新作映像において東日本大震災後に建設された巨大防波堤を歩き続ける人物が映し出される。ドイツのアーティスト、ミーシャ・ラインカウフの展示では、地上では行き来が困難な地域の、でも実は海底にもある見えない国境を作家自身がてくてくと横断する映像作品が展示される。この作品は、国境の影響力やその強度を問い、ある種の遊び心を持って、身体を使って自由な空間を切り開く。
歩くことから、人間にとっては不可能な「飛ぶ」ことへと理想の美を追求したクラシックバレエの規範、あるいは芸術表現における女性の「美」そのものへの挑戦をパフォーマンスへと化したのは、ヨーロッパの舞台芸術シーンを席巻し、初来日となるフロレンティナ・ホルツィンガーである。絶対的な美の規範を、あっさりとパロディ化してしまうその手法をぜひ目撃していただきたい。演者と観客の対話により上演が組み上がっていくのは、オーストラリアとヨーロッパを行き来しながら活動するサマラ・ハーシュによる作品である。会話がてくてくと展開することにより出来上がるような上演空間と時間は、その場にいる者だけが体験できる唯一無二のものである。この両作品では、知識や伝統をどのように世代から世代へと受け継いでいくのか、ということも大きな問いである。
スペースノットブランクの新作では、松原俊太郎による新作戯曲、映像表現と舞台表現の3つの要素における多様な行き来が体験できるであろう。そこでドラマティックに解体され、再生成されるものが何か、ぜひ劇場で体験していただきたい。テキストと身体の拮抗する関係性を作品化するのは、チーム・チープロも同様である。京都での作品創作と発表が2年目となるこのユニットは、今回は女性性と相撲の四股を参照しながら新たな儀式を形成する。
個人の旅や視点を通じて、大きな歴史の物語と未来の物語を見つめ直すのは、タイの演出家、ジャールナン・パンタチャートとイランの演出家、アーザーデ・シャーミーリーである。パンタチャートは、タイとミャンマーの歴史的関係に注目し、誰が壮大な歴史の物語を書くのか、疑問を呈する。シャーミーリーは2070年を舞台に、私たちが自分や他人の人生をいかに記憶・記録するかを問いかける。
ほぼ10年ぶりの日本での公演となるイギリスのパフォーマンス・グループ、フォースド・エンタテインメントの2作品においては、あるシステムや枠組みにおける変化、それに対する希望が打ち砕かれることや、それを遊んだりすることなどを読み解くことができる。両作における、帰結の見えない状況で空転するかのような戯れは、「いま」何が可能かについて考えるように私たちを誘うだろう。
梅田哲也、ティノ・セーガルの作品は、いずれも観客が自ら歩き、発見することを求める。梅田の作品では、観客はかつて別の用途で使われていた建物のなかで、その空間を存分に体験しながら日常とも上演ともつかないてくてくを体験し、新しい日常の歩き方を発見するかもしれない。ドイツを拠点とするセーガルの作品は、京都市京セラ美術館の日本庭園でフェスティバルの全期間にわたって展開される。観客は、自分のために歌ってくれる人物に出会うために、自ら庭に足を踏み入れる。
フェスティバルを開催する京都、そして関西地域をアーティストの視点からリサーチし、今後の創作基盤につなげていくKansai Studiesは3年目を迎える。このリサーチプログラムの一旦の区切りとしてこれまでの探求を演劇作品化し、関西地域での行ったり来たりのてくてくをみなさんに共有する。リサーチと、そこから創造されるものが並列に、あるいはせめぎあいながら共存する作品は、どのような表現を獲得するだろうか。
エクスチェンジプログラムであるSuper Knowledge for the Future [SKF] においては、Showsに関係するトークやワークショップに加え、歩くこと、あるいはそこから発展するアートとポリティクスの関係を紐解くトークなど、多様な角度からフェスティバルに参加していただけるプログラムを考えた。
フェスティバル継続の危機について
最後に観客のみなさんには、このフェスティバルがこれまでになく継続の危機にあることをお伝えしたい。新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況の変化が大きく影響し、このフェスティバルの運営主体である実行委員会が担う予算は、コロナ前と比べて半分程度減少することとなった。公私、国内海外さまざまな助成金を組み合わせてなんとか予定しているプログラムを実現させるために尽力しているが、予算額が減少したことに加えて渡航費のこれまでにない高騰、円安の影響も非常に大きい。そこで、この文章を完成させようとしている2022年6月のいま、予算を補填するためのクラウドファンディングに向けて準備を進めている。
今年度はこのような形でみなさんとプログラムを共有することを目指しているが、その先の継続のあり方についても対応策を講じていかねばならない。急激に変化するリアリティをまなざすための「実験」を舞台芸術において実践していくこのフェスティバルだからこそ、時代と並走していきたいと強く願っている。いかに継続し、対話を続けていくのか。これからもぜひ、共に思考し、このフェスティバルの挑戦をサポートしていただければ幸いである。
KYOTO EXPERIMENT共同ディレクター
川崎陽子 塚原悠也 ジュリエット・礼子・ナップ