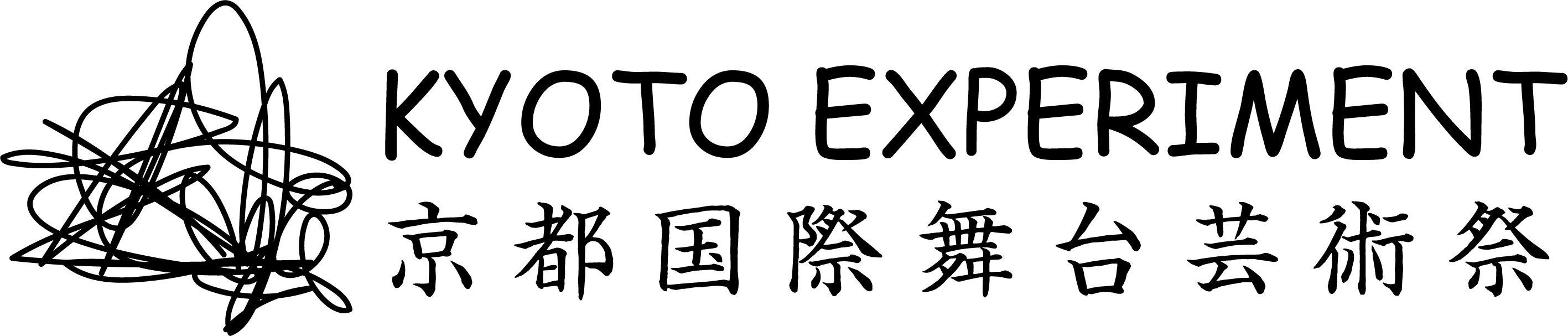news
【批評プロジェクト 2023】選出作品発表!
2023.12.16

KYOTO EXPERIMENT 2023では、対象演目のレビューを募集する批評プロジェクト 2023を実施しました。
演劇批評家の森山直人氏による審査を経て、3件のレビューを選出しました。森山氏がメンターとなってアドバイスを行い、ブラッシュアップ期間を経て完成したレビューを、本ウェブサイトのmagazineページにて公開します。今回選出された3件のレビューからさらに最終選出作品1件を選出します。最終選考結果については、12月22日(金)にウェブサイトで発表します。
【選出レビュー】
(五十音順)
唐沢絵美里
影が-狩人(わたしたち)を-獲物にする
安川奈那
曖昧化される境界―影としてのAIから障がい / 健常を問う
山口真由
「席につく」ということ―『影の獲物になる狩人』に見る、もの言うことの権力性
【審査、メンター】
森山直人(演劇批評家/多摩美術大学美術学部・演劇舞踊デザイン学科教授)
【対象作品】
バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』
2023年10月7日(土)–10月8日(日)
【全体講評】
今回の劇評プロジェクトの対象となった演劇作品『影の獲物になる狩人』(バック・トゥ・バック・シアター)は、一見、とてもシンプルな構造をもっているように見えます。大きな舞台装置はほとんどなく、上演時間も約60分。登場人物もたった3人しか出てきません(ただし、3人の「背後」にはAIが存在していますが)。けれども、いざ批評の言葉を紡ぎだそうとすると、案外難しかったのではないでしょうか。今回もまた、挑戦してくださった方の作品は、どれも力作揃いでしたが、それぞれの文体のなかに、何らかの形で「難しさ」が顔をのぞかせていたのも印象的でした。
当り前ですが、私たちは、観客として劇場に足を運び、作品に対面します。ただ、現代演劇の場合、この「対面」の質に、作品の違いに応じてさまざまなヴァリエーションがある、ということは、多くの方がお感じになっているのではないでしょうか。作品が、ひとつの完成された統一体として、私たちの目の前に立ち現われ、私たちはただ息をのんで向かい合うほかない、というタイプの「対面性」もあれば、そうでない形のものもある。本作の場合は、一見、通常の対話劇のような形態で進行するので、観客席という〈暗闇にまぎれた安全地帯〉は、さほど脅かされていないようにも見える。ところが、実は、目前で行われている対話や状況に対して、いざ、何かを感じたり、心の中で言葉にしようとしたりした瞬間に、自分自身が無意識にどこにいるのか、何に依拠して物を見てきたのかを自覚せざるをえなくなってしまうのです。
何かを感じ、考えているその瞬間の自分自身が、まさしく「当事者」として、自分自身の中で浮彫りになってくる。『影の獲物になる狩人』は、そういう形で観客を、そこで行われているもののただ中へと巻き込んでいく力を持っていたように思いました。
たとえば、この作品では、「健常者 / 障害者」という社会的レッテルが、明らかに主軸のひとつをなしています。けれども、たとえば、舞台上にいる登場人物/俳優たちを、いつのまにか「障がい者同士の対話」――あえてこのセンテンスでは「がい」をひらがなで書きますが――というふうに見ている自分に気づいたとき、舞台上の3人はもはやその枠ではとらえられない場所にいます。お互いの権利と自尊心をめぐって、マウントの取り合いをしていたりする3人の姿を、「まるで健常者と同じようにマウントを取り合っている」と感じるとしたら、「健常者と同じように」という言葉遣いの中に、その人がふだん依拠している意識があざやかに立ち現れてしまうのだし、「障がい者のなかにも差別があるのだ」と感じるとしたら、「障がい者のなかにも」という言葉遣いがたちまち自分自身に跳ね返ってくる。KYOTO EXPERIMENTのEX公式ウェブサイトにも掲載されているアサダワタル氏の批評でも指摘されていますが、まさにこの作品で問題になっているのは、「言葉にしようとすること」や「言葉で論じようとすること」そのもののなかにある、この上なく身近にあるありふれた政治性なのではないか・・・。
バック・トゥ・バック・シアターは、そうした問題を、ある種のユーモアとともに私たちに差し出してくれていたようにも思えました。それゆえ、それらの「問題」を、あまりに「深刻」に翻訳しようとすると、かえってレッテルの派生物のようなものに引き寄せられてしまう・・・。作品のもつそういう構造自体を批評的にとらえることが、まさに言葉で表現するほかない「批評」にとっては、意外に難しい。今回、最終選考に残った3作品は、それぞれの見る立場や受け止め方は違うのですが、本作の、そのようないわば「シンプルな複雑さ」を、何らかの形でうけとめ、可能なかぎり意識的に引き受けることで、作品の問いかけに、一歩踏み込んだ応答をなさっていたように思えました。
(1) 安川奈那さんの批評は、「AIの暴力性」という観点からなされたものですが、作品の本質を短いフレーズでとらえる言葉の的確さと、作品のひとつひとつのディテールを言葉にしていく作業の粘り強い手つきが、この作品の「複雑さ」をおのずと描き出すことに成功しているように思いました。その上で、日本語上演に特有の問題――字幕の翻訳と劇場空間の広さ――についても、重要な論点を提出なさっていました。
(2) 山口真由さんの批評は、この作品の構造を、「席につくこと」あるいは「席を用意すること」という観点からあざやかに浮かび上がらせていて、思わず私自身もはっとさせられました。単純な舞台装置(黄色いテープや演台)の意味を論じる論じ方も、「発言できる/できない」こと、という、もっともプリミティヴな政治性のテーマと溶け合って、説得力ある議論が展開されていました。
(3) 唐沢絵美里さんの批評は、「現代日本社会における差別」という観点を重視しながら、作品そのものに対する率直な共感を批評の言葉に翻訳なさっていた点が、強く印象に残りました。終演後に流れていたマイケル・ジャクソンの楽曲の意味に対する鋭い応答は、批評言語に特有の論理と感性とが共振した、忘れがたいフレーズを形作っていたように思いました。社会言語学でいう日本語の「女ことば」で字幕を翻訳することに対する問題提起も貴重です。
(審査・メンター 森山直人)