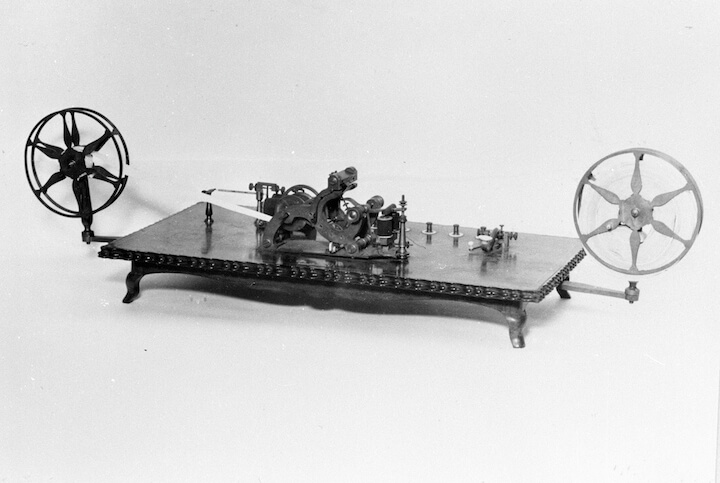【コラム】もしもし?! (内野儀)
2021.10.12 (Tue)
“もしもし?!”
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、オンラインでの対話などにより目の前には存在しない、不在の身体に呼びかけることが多くなった。いまここにいる/いない他者の声や、いま起きている/起きていない音にいかに耳を傾けるのか、これまで以上に問われているのではないでしょうか。「もしもし」と呼びかける主体はわたしなのか、それともわたしは呼びかけられているのか。そして、見えない「もしもし」の向こうをいかに想像していくのか。ここでは、今回のキーワード“もしもし?!”を出発点に、さまざまな視点からのコラムを展開します。
眼の前に置かれたスマホに電話がかかってくる。出ると、「もしもし?」と来る。こちらも「もしもし」と応える。しばらく間がある。どうしよう……。ただ、そこから先は、サミュエル・ベケットの『わたしじゃないし』 (1972) が電話の向こうで演じられる?語られる?のを聞くことになる。ベケットのぐるぐる回るようで難解な言葉に飽きてくると、見透かされたようにまた、「もしもし?」と、原作テクストにはない呼びかけがあり、はっとまた集中することになる。何しろわたしひとりへの呼びかけなのだ。
いわゆるコロナ禍にあって、この電話を使った上演 (『もしもし、わたしじゃないし』、以下、『もしもし』と表記) を考案したのは、かもめマシーンを主宰する萩原雄太である。語るのは俳優の清水穂奈美。2020年9月に初演されたが、わたしは、早稲田大学にある演劇博物館の他に誰もいない2階展示スペースで、2021年8月2日午後6時過ぎ、この電話を受けることになった。
不思議な身体的な経験だったが、ある意味暴力的な一対一の関係性への誘いとも感じられたためか、わたしは、電話の向こうの言葉を聞き流しながら、展示そのものを見て回るという逃避行動に出た。が、やがて、スマホからの音声に集中できるような心身の状態になったようで、展示室の外廊下にあった椅子に腰かけ、最後まで耳を傾けることができた。
本来の想定は個人所有の携帯電話にかかってくるのだが、このバージョンだけ博物館の展示への協力公演ということで、かなり様相が異なっていた。同博物館ではちょうど、「ロスト・イン・パンデミック」 (早稲田大学坪内博士記念演劇博物館2021年度春期企画、会期2021年6月3日~8月6日) なる展示が行われていたからだ。上演開始は、博物館の閉館時間後に設定されていて、主要な展示スペースを見ることはできるものの、展示用映像の再生は行われていなかった。それでも、ポスターや衣装、舞台装置の模型、あるいは台本といった、コロナ禍によって上演中止や延期を余儀なくされた舞台作品にかかる資料を、詳細な年表とともに、見ることができた。実際、展示の一角に、『もしもし』についての紹介があり、そこにぽつねんと、スマホが一台置かれていたのだ。そして、時間になるとそこに電話がかかってきて、上演がはじまる、という仕組みだった。
同作品については、萩原自身が、2021年7月16日付けのnoteに「なぜ、電話演劇か ── 薄暗い場所から公共を生み出すこと」[1]という優れた論考を寄せており、わたしとして、特に付け加えたいことはない。ただ、原理的な問題として、萩原が、コロナ禍であろうがなかろうが、「演劇とは何か」という問いに向き合いつつ、新たな公共の概念を、この電話演劇という独特のフォーマットによって、提示しようとしていることだけは確認しておきたい。
「ロスト・イン・パンデミック」の、少なくともわたしが見ることができた展示の大半は、上演が中止あるいは延期になったために、「失われた」上演にかかる諸資料である。詳細な年表もよくできていたし、他方、出版物としては、通常の展覧会カタログとは異なる歴史的価値のある論集とでも呼ぶべき大部の『Lost in Pandemic―失われた演劇と新たな表現の地平』は、かなり早い段階の6月30日付けですでに出版されてさえいる。
ではこの間、日本語圏の演劇実践は、展示の副題にある「新たな表現の地平」を目指したのだろうか?本展示では、『もしもし』を含むごく少数の事例が最後のパートで紹介されていたが、コロナ禍をともに過ごしてきたわたし個人の経験から言っても、いわゆる業界全体においては、そのような試みはほぼ皆無だったのではないか。
たしかに多数の利害関係者が結集した経済支援のネットワーク (「緊急事態舞台芸術ネットワーク」) が構築され、政府にロビイングをかけるという直接行動は目を引いたが、それらは所詮、「元通り」になるまで耐える、という体制順応的な対応だった。いや、「元通り」どころか、演劇は劇場という閉鎖空間におけるライヴの上演であることが自明視されたあげくに、コロナ禍だからこそ、「元通り」になることには、重大な価値があるという倒錯的な特権意識が全体化するような状況になったのである。それはちょうど、20世紀初頭の映画の時代や20世紀末のデジタル化の時代において、メディウムとして劣勢に立っていることにむしろ開き直り、だからこそライヴのパフォーマンスには自明の価値があるとしてきた演劇の歴史を繰り返しているかのようだった。
『もしもし』は、すでに明らかなように、こうした状況への批評的応答である。ただし、萩原が議論するような「新たな公共」という高次の概念のずっとずっと手前の、コロナ禍で問われたはずの「演劇とは何か」という原理的な水準においてもそうであることが何より重要だ。わたしは『もしもし』に参加して、日本でも早くから紹介されたヨーロッパにおけるコロナ禍についてのイタリアの哲学者ジョルジュ・アガンベンの議論と、それが圧倒的な少数派として抑圧されていくプロセスを思い起こさずにはいられなかった。
アガンベンの一連の発言は、すでに日本語で一冊の本にまとまっている[2]。粗雑を承知でまとめると、本書を通じてアガンベンは、「個人の自由=私権を奪われるくらいなら、新型コロナウィルスで死んでもかまわない」と言っている、とわたしは理解している。「死んでもかまわない」が極論にすぎるなら、コロナを口実に私権を奪おうとする権力に「徹底して抵抗する / せよ」と煽っている。しかしわたしは、すでに触れたように、この1年半、演劇界のほぼ100%が体制順応=「自粛する=私権を手放す」であるように見えていた。つまり、日本語圏の演劇実践者に、アガンベンはいないのではないか、と疑っていた。
その疑念が、『もしもし』を経験して氷解した。いる、ではないか、と。こうしてわたしは、アガンベンも参照しながら、演劇と公共について、つまりは、演劇という形式の本来的暴力性と他者の問題について、「もしもし」という呼びかけ / 呼び出しを契機として、コロナ禍であろうがなかろうが、萩原 (他にもきっといるはずだ) とともに考える準備が整ったと思えるようになった。つくづく近代主義だと自戒はあるものの、わたしはやはり、前近代とポストモダンを案配しながらサヴァイヴするという今流行のJ的戦略には乗れない。そんなわたしにとって、「もしもし?!」は今もっともクリティカルなテーマなのである。
[1]https://note.com/kamomemachine/n/n7b5fb00f22ae
[2] 『私たちはどこにいるのか―エピデミックとしての政治』高桑和巳訳、青土社、2021年
内野儀
1957年京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。博士 (学術)。学習院女子大学教授。専門は表象文化論。著書に『メロドラマの逆襲』 (1996 ) 、『メロドラマからパフォーマンスへ』 (2001 )、『「J演劇」の場所』(2016)。